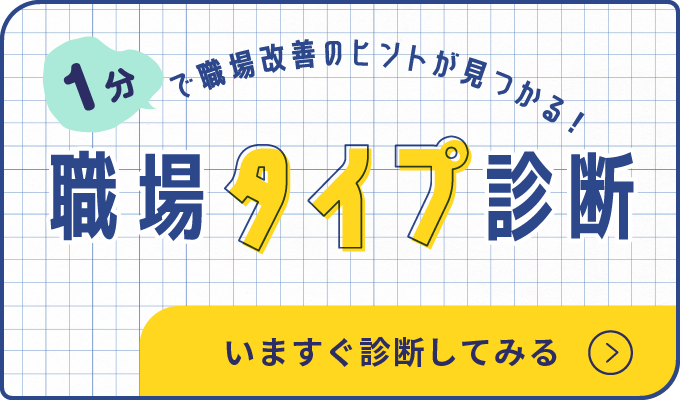産業医面談の進め方と注意点 人事・総務担当者が面談前後にやるべきこと、面談を拒否された場合の対応も解説!
2025.08.29

従業員の健康管理と企業の安全配慮義務を果たす上で不可欠な産業医面談。重要なことは理解していても、「産業医面談って、具体的にどう進めるの?」「人事・総務として、どんな準備や注意が必要?」など、その具体的な流れや担当者が果たすべき役割について、不明点がある方も多いのではないでしょうか。
本記事は、人事・総務担当者の方々が産業医面談を円滑かつ効果的に実施できるよう、面談前の準備から実施、記録、そして面談後のフォローアップまで、実践的なプロセスを詳細に解説します。さらに、よくある疑問点にもお答えします。産業医面談を適切に運用したい、という方はぜひ参考にしてみてください。
目次
産業医面談の進め方と注意点(1)面談前の調整と準備
産業医面談を円滑に進めるためには、事前の準備と調整が不可欠です。人事・総務担当者はもちろん、従業員自身も準備を行うことで、面談の効果を最大化できます。
1.面談対象者の選定
産業医面談の対象者となる従業員を決定します。たとえば、長時間労働者、ストレスチェック制度の高ストレス該当者、健康診断において異常所見があった従業員などが対象者になり得ます。それぞれの詳しい要件を確認して適切に決定しましょう。その他、自らの健康に関して相談がある従業員から面談の希望があった場合にも産業医面談を行います。従業員がいつでも相談できるように、産業医による健康相談の申し込み方法を周知しておくことが重要です。
2.従業員へ面談を案内
産業医面談の日時、場所を決定したら従業員へ面談の案内をします。その際、周囲に産業医面談を受けることを知られないよう、封書やメールを用いるなどの配慮が必要です。面談の目的や守秘義務について明確に説明をし、従業員に面談に安心して参加してもらえるようにします。面談場所も、プライバシーが確保され従業員が安心して話せる環境にしましょう。
3.産業医への情報提供
安衛法第13条4項では、産業医へ労働者の健康管理等を適切に行うための必要な情報を提供しなければならないとされています。面談の目的に合わせて必要な情報を収集し、産業医に事前に申し伝えます。これらの情報は、産業医が適切な助言や意見をする上で重要な判断材料となります。
提供される情報の例
- ● 従業員の健康診断結果
- ● 従業員の勤怠状況(勤怠に関わる診断書なども含む)
- ● 従業員の残業時間
- ● 従業員のストレスチェックの結果
- ● 就業上の「講じた措置又は講じようとする措置」に関する内容
プライベートな情報が含まれることから、産業医へ提供されることに不信感を持つ従業員もいるかもしれません。あらかじめ就業規則などに定め、必要な範囲内での個人情報の利用について事前に周知し、理解をしてもらうことも重要です。
📝 従業員が準備しておくと良いこと
従業員は、面談に臨むにあたり、自身の健康状態、業務内容、現在の困りごと、職場環境に対する懸念などを整理しておくことが推奨されます。具体的には、以下のような点を事前に考えておくと良いでしょう。
- ✦ 体調の変化や気になる症状(いつから、どのような症状か)
- ✦ 業務内容や業務量、人間関係におけるストレス要因
- ✦ 睡眠、食事、運動などの生活習慣
- ✦ 産業医に聞きたいことや相談したいこと
- ✦ 希望する就業上の配慮
これらの情報をメモにまとめておくと伝え忘れがなくなり、産業医に今の状況を正確に理解してもらうことができます。
産業医面談の進め方と注意点(2)面談の実施
面談は産業医が実施します。産業医は従業員の現在の健康状態、業務内容、職場環境、生活習慣などについて詳しくヒアリングを行い、専門的な知識に基づいて、従業員が抱える健康問題やストレスの原因を特定し、適切な助言を行います。必要に応じて、専門医療機関への受診を推奨したり、生活習慣の改善策を提案したりすることもあります。
また、産業医は就業上の措置が必要な場合「産業医意見書」を作成します。この意見書は、従業員の健康情報を保護しつつ、企業が必要な措置を講じるための公式文書となります。
ただし、産業医が企業に提供できる情報は、従業員の同意を得た上で、就業上の措置に必要な範囲に限定されます。詳細な病状など、機微な個人情報は守秘義務の対象となり、原則として企業に開示されません。人事・総務担当者はその点をあらかじめ理解しておきましょう。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせる産業医面談の進め方と注意点(3)面談後のフォローアップと就業上の措置
産業医面談は、実施して終わりではありません。面談で得られた情報や産業医の意見に基づき、適切なフォローアップと就業上の措置を講じることが、従業員の健康維持と生産性向上に不可欠です。
1.産業医意見書の確認
産業医から意見書が提出されたら、人事・総務担当者はその内容を速やかに確認します。意見書には、主に以下の内容が記載されます。
- ● 従業員の健康状態
- ● 就業上の配慮に関する具体的な意見(労働時間の短縮、深夜業の制限、作業内容の変更、配置転換、休養の必要性など)
- ● その他、職場環境改善に関する助言など
不明な点があれば産業医に質問をして詳細な説明を求めましょう。この意見書は、「面接指導の結果に基づく意見」として、事業者に適切な措置を講じる義務を課す根拠となります。(労働安全衛生法13条⑤、66条の5①、8⑤、8の2②など)
2.意見書に基づく就業上の措置の実行
産業医の意見書を受け取ったら、担当者はその意見を尊重し、従業員の健康状態に応じた適切な就業上の配慮を講じる義務があります。これらの措置は、従業員の健康を守り、安全で快適な職場環境を提供するために非常に重要です。
担当者は、従業員本人、産業医、そして現場の状況を総合的に考慮して、以下の具体例を参考に措置を決定します。
これらの配慮は、従業員や上司と十分に話し合い、合意の上で決定することが重要です。一方的な決定は、従業員のモチベーション低下や不信感につながります。また、配慮の期間を設定し、定期的にその効果を評価して、必要に応じて見直しを行いましょう。
産業医面談の進め方と注意点(4)面談記録の保管
面談記録は、個人情報保護法および労働安全衛生法に基づき、厳重に管理する必要があります。具体的には、以下の点に留意して記録を保管します。
- ● 保管場所: 施錠可能なキャビネットやアクセス制限された電子データとして保管します。
- ● アクセス権限: 閲覧できる者を必要最小限に限定します。
- ● 保管期間: 法令で義務づけられた期間(5年間)適切に保管します。
- ● 廃棄: 不要になった場合は、個人情報が漏洩しないよう適切に廃棄します。
これらの記録は、将来的な健康管理施策の立案や、同様のケースが発生した際の参考資料としても活用されます。
産業医面談のよくある疑問
ここまで産業医面談のプロセスや注意点を解説してきました。最後に、産業医面談にまつわるよくある疑問を紹介します。人事・総務担当の皆さんはぜひ参考にしてみてください。
Q1.従業員が産業医面談を拒否した場合はどう対応すればいい?
産業医面談は、特定のケースを除き、従業員に受診を強制できるものではありません。ただし、労働安全衛生法において事業者に実施が義務づけられている面談(例:長時間労働者への面接指導)においては、従業員には面談を受ける努力義務があると解釈されます。
従業員が面談を拒否した場合、人事・総務担当者は以下の点に留意して対応することが求められます。
- ● 面談の目的とメリットの再説明: 不調の早期発見や悪化防止、適切な就業上の配慮を検討するための重要な機会であることを丁寧に説明します。
- ● プライバシー保護の徹底: 産業医には守秘義務があること、面談内容が本人の同意なく事業者に共有されることはないことを明確に伝えます。
- ● 代替手段の検討: 対面での面談に抵抗がある場合は、オンライン面談や電話面談の可能性を提示するなど、従業員が安心して話せる環境を提案します。
- ● 記録の保持: 面談を打診した日時、内容、従業員が拒否した事実、その理由、企業がどのような説明や配慮を行ったかを詳細に記録に残しておくことが重要です。
Q2.産業医面談の後に、従業員の上司から「詳細な内容を教えてほしい」と求められたら?
産業医面談の内容には、病名や治療内容などのセンシティブな情報が含まれることがあります。これらは本人の同意なしに上司へ開示することはできません。産業医から企業へ提供されるのは、就業上の配慮に必要な範囲(例:残業制限、深夜業の禁止、配置転換の必要性など)に限定されます。
上司に説明を求められた場合は、以下のように対応します。
- ● 原則を説明する: 「産業医には守秘義務があり、詳細な病状は共有できない」ことを明確に伝えます。
- ● 必要な情報のみ伝える: 産業医の意見書に基づき「業務遂行に関して必要な配慮」だけを説明します。
- ● 従業員本人の合意を確認する: もし詳細説明が不可欠と考えるなら、本人の同意を得てからにすることが必須です。
この対応を徹底することで、従業員のプライバシーを守りつつ、上司の理解も得やすくなります。
Q3.産業医の意見と上司の考えが食い違った場合はどうすればいい?
産業医は医学的見地から意見を出しますが、現場の上司は業務上の都合から異なる判断をすることもあります。この場合、人事・総務担当者が調整役となり、①産業医の意見を尊重する、②従業員本人の意向を確認する、③業務上の制約を考慮する、の3点を踏まえて合意形成を図ります。 必要に応じて、産業医・上司・人事が同席しての三者面談を設定することも有効です。
まとめ
本記事では、産業医面談の具体的なプロセスと、人事・総務担当者が果たすべき重要な役割や注意点について詳しく解説しました。面談前の準備から実施、記録、そして面談後のフォローアップと就業上の措置まで、各段階で求められる対応を理解いただけたのではないでしょうか。 産業医面談は、単なる形式的な手続きではありません。従業員が安心して健康に関する相談ができ、企業が安全配慮義務を適切に果たすための重要なコミュニケーション機会です。本記事が、貴社での産業医面談の適切な運用と、従業員の心身の健康、ひいては企業の持続的な成長に貢献できれば幸いです。
この記事の要点
- 面談前の準備が不可欠である。人事・総務担当者は、面談の目的や守秘義務について従業員に明確に説明し、プライバシーが確保された環境を整える必要がある。
- 産業医が作成する意見書は、従業員の就業継続の可否や必要な配慮事項を記載しており、企業が措置を講じる上での重要な根拠となる。
- 企業には、産業医の意見を尊重し、労働時間や業務内容の変更、配置転換などの具体的な就業上の措置を講じる義務がある。
- 就業上の措置を決定する際は、従業員や上司との丁寧な話し合い(合意形成)が不可欠であり、一方的な決定は避けるべきである。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- ご要望をヒアリングし嘱託産業医を紹介
- 産業医と会社と従業員を“つなぐ”サービスを提案
自社に最適の産業医を
お探しの企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!