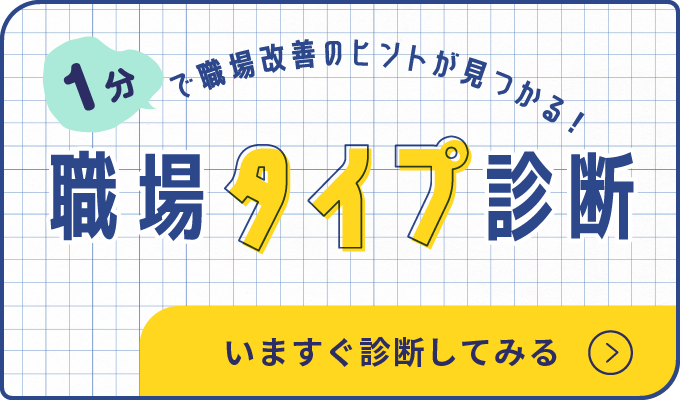『産業医が役立たず』と感じてしまうのには理由があった!?
5つの理由と解決策、見直したいポイントを解説
2025.08.28

しばしば耳にする「産業医が役立たずに感じてしまう」というお声。詳しくお伺いしてみると、「専門性のミスマッチ」「コミュニケーション不足」「役割への誤解」など、共通した原因が隠れていることがあります。本記事では、産業医を有効活用できていない、と感じる原因を深掘りし、それぞれに対する具体的な解決策を徹底解説します。さらに、失敗しない産業医の選び方や、効果的な付き合い方、最大限に活用するための実践的なノウハウを網羅的にご紹介。この記事が、産業医との関係を改善し、企業の健康経営を推進する具体的なヒントになれば幸いです。
目次
「産業医が役立たず」と感じてしまう理由
「産業医が役立たず」と感じてしまう背景には、大きく5つの原因があります。
- 1 専門性のミスマッチ
- 2 コミュニケーション不足
- 3 会社への関与の薄さ
- 4 契約内容と期待値のギャップ
- 5 会社側の理解不足
誤解や期待のズレが、産業医の貢献を会社や従業員が実感できない状況を生み出しているケースが少なくありません。この記事では、以上5つの理由の詳細と対策を、詳しく解説していきます。
理由1:専門性のミスマッチ
原因
近年、メンタルヘルス不調者の増加やハラスメント問題への対応、長時間労働対策など、複雑かつ専門的な知識が求められる場面が増えています。しかし、実際に依頼した産業医の専門性が、企業の期待や現状の課題と合致しない場合、「役立たず」という評価につながることがあります。 例えば、メンタルヘルス対策を強化したいと考えているにもかかわらず、選任した産業医が身体疾患の専門医であり、精神科医や心療内科医としての経験や知識が不足している場合、具体的な助言や支援が期待できないと感じるかもしれません。また、最新の労働衛生に関する法令やガイドラインの知識が不足していたり、特定の業界における健康課題への理解が浅かったりすることも、専門性に対する不満の原因となります。 期待する専門性と、実際に提供される知識・経験にギャップがあることで、企業側は「具体的な問題解決につながらない」「表面的なアドバイスしか得られない」と感じ、産業医の存在意義に疑問を抱いてしまうのです。
対策:専門分野や実績の確認、求めているスキルの明確化
適切な専門性を持つ産業医を選び、その能力を最大限に引き出すために以下の対策を講じましょう。
産業医の専門分野や実績を確認する
産業医には、内科医、精神科医、外科医など様々な専門分野を持つ医師がいます。例えば、企業が抱える健康課題がメンタルヘルスであれば精神科医の知見が、生活習慣病対策であれば内科医の知見がより役立つでしょう。契約前に、産業医の医師としての専門分野や、産業医としての具体的な実績(例:メンタルヘルス対策の実績、特定業種での経験、健康経営への貢献事例など)を詳細に確認することが重要です。 紹介会社を利用する場合は、企業の課題を明確に伝え、それに合致する産業医の候補を複数提示してもらい、それぞれの専門性や実績を比較検討しましょう。
求めているスキルを明確にする
産業医に求められるのは、医学知識だけではありません。企業の状況を理解し、従業員と円滑にコミュニケーションを取り、具体的な改善策を提案できる能力も不可欠です。契約前に、自社が産業医に求める具体的なスキルをリストアップし、それを満たす人材を選定基準としましょう。
例えば、以下のようなスキルが挙げられます。
- コミュニケーション能力: 従業員や経営層、人事労務担当者と円滑な対話ができるか。
- 企業理解: 自社の事業内容や企業文化、組織体制を理解しようと努める姿勢があるか。
- 提案力・実行力: 健康課題に対して具体的な解決策を提案し、その実行を支援できるか。
- 法令知識: 労働安全衛生法など、関連法規に関する知識が豊富か。
- 情報収集力: 最新の医療情報や労働衛生に関する情報を常にアップデートしているか。
産業医の実績と求めているスキルが合わない場合は、まずは産業医と相談してその溝が埋められるものなのか、話し合いをしてみましょう。どうしても埋められない場合は、新しい産業医を探すことも視野に入れて検討したほうが良いかもしれません。
理由2:コミュニケーション不足
原因
産業医がその役割を最大限に発揮するためには、企業の人事担当者、管理職、そして従業員との円滑なコミュニケーションが不可欠です。コミュニケーションが不足していると、産業医を「役立たず」と感じてしまう大きな要因となります。
具体的なコミュニケーション不足の例としては、以下のような状況が挙げられます。
- 情報共有が不足: 産業医からの活動報告や健康状態のフィードバックが乏しい、あるいは企業側から職場状況・課題・従業員特性の提供が滞っている。
- 相談しづらい・形式的対応: 従業員が相談をためらう/相談しても形式的と感じる。産業医の多忙さや威圧的な態度が要因になることがある。
- 現場理解が浅い: 企業の状況や従業員の背景を十分に掴めず、一般論に終始して「自分たちを理解していない」と感じさせてしまう。
- 部門連携が弱い: 人事・総務・現場管理職などとの連携が乏しく、問題の早期発見や解決が遅れる。
産業医と企業・従業員間のコミュニケーションが円滑でないと、信頼関係が構築されず、産業医の助言や提案が職場で十分に活かされなくなってしまいます。
対策:共有の場を設ける、従業員からのフィードバックを集める
以下の対策を講じて、産業医との連携を強化しましょう。
定期的な情報共有の場を設ける
安全衛生委員会への参加だけでなく、産業医と人事労務担当者、衛生管理者との間で定期的な情報共有の場を設けることが重要です。月1回、または隔週など、頻度を決めてミーティングを実施し、以下の情報を共有しましょう。
- 従業員の健康状態に関する傾向(健康診断結果の集計、ストレスチェックの結果概要など)
- 休職者や復職者の状況
- 職場での新たな課題や問題点(長時間労働、ハラスメント相談など)
- 産業医からの助言に対する進捗状況
これにより、産業医は企業の「今」をリアルタイムで把握し、より的確なアドバイスを提供できるようになります。
従業員からのフィードバックを収集する
従業員との個別面談・健康相談の機会が多い場合、産業医の活動が従業員にどのように受け止められているかを把握することも重要です。匿名性を確保した上で、従業員からの産業医に関するフィードバックを収集する仕組みを検討しましょう。例えば、以下のような方法が考えられます。
- 産業医面談後のアンケート(任意)
- 社内目安箱や専用メールアドレスの設置
収集したフィードバックは、産業医との関係改善や今後の活動計画に活かすための貴重な情報源となります。ただし、プライバシー保護には最大限配慮し、産業医の個人情報が特定されるような内容の開示は避けましょう。
理由3:会社への関与の薄さ
原因
産業医の重要な職務の一つに、職場巡視や安全衛生委員会への参加を通じて、職場の健康リスクを把握し、改善提案を行うことがあります。しかし、これらの活動が形骸化していたり、産業医の会社への関与が薄いと感じられたりする場合、企業側は「役立たず」という印象を抱きがちです。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- 産業医が職場を訪れても、短時間で通り過ぎるだけで、具体的な危険箇所の確認をほとんど行わない。
- 安全衛生委員会に定期的に出席するものの、具体的な意見や改善提案を積極的に行わず、議事録に名前が載るだけの存在になっている。
- 職場環境や従業員の健康課題について、問題点を指摘するだけで、その解決に向けた具体的なアクションプランや、企業が実行可能な提案がない。
産業医が企業の健康課題に深く関与せず、表面的な業務に終始していると、企業側は「何のために産業医を置いているのか分からない」と感じ、その価値を見出せなくなってしまいます。
対策:安全衛生委員会における役割の明確化、職場巡視の目的・課題の共有
産業医が「会社への関与が薄い」と感じられる場合、それは産業医の役割が明確に定義されていない、あるいは会社側が産業医の専門性を十分に活用できていないことが原因かもしれません。産業医が企業活動に深く関与できるよう、具体的な役割と目的を共有しましょう。
安全衛生委員会での役割を明確にする
安全衛生委員会は、産業医が企業の安全衛生状況を把握し、意見を述べる重要な場です。単なる「出席者」としてではなく、必要な際に意見を述べ、改善提案を行う「専門家」としての役割を明確にしましょう。
具体的には、委員会の議題設定に産業医の意見を反映させたり、特定の健康課題について産業医からの情報提供や専門的な解説を求めたりすることが有効です。また、産業医の意見がどのように施策に反映されたかをフィードバックすることで、産業医のモチベーション向上にも繋がります。
職場巡視の目的や課題を明確にして産業医に共有する
職場巡視は、労働安全衛生法で義務付けられている産業医の重要な業務の一つです。しかし、形式的な巡視に終わってしまうと「役立たず」と感じられる原因になります。巡視の前に、会社側から産業医に現在の職場の課題や懸念事項を具体的に共有しましょう。
例えば、「特定の部署でストレスチェックの数値が高いので、その部署の環境を重点的に見てほしい」「新しい機械を導入したので、その作業環境のリスクを確認してほしい」など、具体的な要望を伝えることで、産業医はより有意義な巡視を行うことができます。巡視後には、産業医からのフィードバックを真摯に受け止め、改善に繋げることが重要です。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせる理由4:契約内容と期待値のギャップ
原因
産業医との契約は、提供されるサービス内容や頻度、費用などを明確に定めるものです。しかし、この契約内容と企業が産業医に期待する役割やサービスにずれがある場合、「役立たず」と感じる原因となります。
よくあるミスマッチの例を以下の表に示します。
契約時に業務範囲やサービス内容を明確にせず、漠然とした期待値だけで産業医を選任してしまうと、後になって「思っていたのと違う」という不満が生じやすくなります。また、契約内容を十分に理解しないまま進めてしまうことも、このミスマッチの一因です。
対策:契約前の要件定義確認の徹底、契約後の定期的な見直し
「産業医が役立たず」と感じる根本的な原因として、契約時に設定した業務内容と、会社が産業医に期待する役割との間にギャップがあるケースが少なくありません。契約前の綿密な要件定義と、定期的な契約内容の見直しが不可欠です。
契約前の要件定義を徹底する
産業医との契約を結ぶ前に、自社が産業医に何をどこまで求めるのか、具体的な業務範囲を詳細に定義しましょう。曖昧な表現を避け、具体的な数値や頻度を盛り込むことが望ましいです。
例えば、以下のような項目を具体的に話し合い、契約書に明記します。
これにより、産業医側も自身の役割を明確に理解し、期待に応えやすくなります。また、将来的な「言った、言わない」のトラブルを防ぐことにも繋がります。
契約内容を定期的に見直す
企業の状況や健康課題は常に変化します。そのため、一度契約した内容が永久に適切であるとは限りません。最低でも年に一度は、産業医との契約内容を見直し、現状に即しているかを確認しましょう。
見直しの際には、これまでの産業医の活動に対する評価や、新たな課題の発生などを踏まえ、業務範囲の拡大・縮小、費用体系の変更などを検討します。双方の合意のもと、契約内容を柔軟に調整することで、常に最適な産業医サービスを受けられるようにしましょう。
理由5:会社側の理解不足
原因
「産業医が役立たず」と感じる最も根本的な理由の一つに、企業側が産業医の本来の役割や法的義務を正しく理解していないケースが挙げられます。産業医は、企業の健康管理体制を支援し、労働者の健康と安全を守る専門家であり、万能な存在ではありません。
よくある誤解としては、以下のようなものがあります。
単なる健康診断の実施者
産業医の役割を健康診断後の面談や意見書作成のみと捉え、それ以外の健康管理活動への期待が薄い。
医師免許を持つ便利屋
医療行為や診断を求めたり、企業内のあらゆる健康問題に介入できると誤解したりする。産業医は職場における健康管理が専門であり、個別の診断や治療を行うことはできません。治療医とは役割が異なります。
法令遵守のための形式的な存在
産業医を法律で義務付けられているから仕方なく置いているだけで、その活用方法を検討しない。
産業医の役割を正しく理解していないことが原因で、企業側が産業医に対して不適切な期待を抱き、結果として「期待に応えてくれない=役立たず」という評価を下してしまうことがあります。労働安全衛生法に基づく産業医の職務(厚生労働省「産業医について」)を把握し、その専門性を適切に活用する視点が欠けていることが、この問題の根底にあります。
対策:産業医の法的役割を理解する、連携体制を構築する
産業医の専門性を最大限に引き出すためには、会社側がその役割を正しく理解し、適切な連携体制を構築することが不可欠です。
産業医の法的義務と役割を把握する
労働安全衛生法に基づき、産業医には様々な法的義務と役割が定められています。これらを会社側が正確に把握することで、産業医に「できること」と「できないこと」の線引きが明確になり、過度な期待や誤解を防ぐことができます。
主な役割としては、健康診断の事後措置、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック後の面接指導、職場巡視、安全衛生委員会への参加、作業環境管理・作業管理への助言などがあります。これらの役割は、厚生労働省のウェブサイトなどで詳細に確認できます。例えば、厚生労働省の「産業医ができること」などの情報源を参照することが推奨されます。
産業医は企業の顧問弁護士や税理士と同じく、専門的な視点から企業と従業員の健康を守る「専門家」であり、単なる健康相談員ではないことを理解しましょう。
産業医との連携体制を構築する
産業医の活動を効果的にするためには、会社内の人事労務担当者、衛生管理者、各部署の責任者、そして経営層との間で、明確な連携体制を構築することが重要です。
具体的には、以下のような体制を整備しましょう。
- 情報共有ルートの確立:誰が、どのような情報を、いつ、どのように産業医に提供するのかを明確にする。
- 担当者の明確化:産業医との窓口となる担当者(衛生管理者など)を定め、情報の一元管理とスムーズな連携を図る。
- 緊急時対応フロー:従業員の緊急事態発生時(メンタルヘルス不調による休職、労災など)に、産業医とどのように連携し、対応するのかのフローを事前に決めておく。
- 経営層の理解と協力:産業医の活動が経営戦略の一部として位置づけられ、経営層がその重要性を理解し、必要なリソースを投じる姿勢を示す。
強固な連携体制は、産業医が企業内の健康課題を早期に発見し、適切な介入を行うための基盤となります。
産業医を効果的に活用するためには従業員への働きかけも重要
多くの企業では、産業医を「健康診断後の面談をする人」あるいは「会社にいるお医者さん」などと、役割を明確に理解していない従業員が少なくありません。しかし、産業医を企業の健康経営を推進するパートナーとして最大限に活用するには、従業員が産業医の役割を理解し、必要な相談ができる環境を整えることも不可欠です。
ここでは、従業員の産業医に対する意識を変え、積極的な活用を促すための具体的な3つのポイントを解説します。
1. 産業医の役割と活動内容を積極的に「見える化」する
従業員が産業医の存在意義を理解していないのは、その活動が見えにくいことが原因です。産業医が日頃から何をしているのかを積極的に周知することで、従業員は「困ったときに頼れる存在」として認識できるようになります。
社内広報や研修で役割を周知する
入社時研修や社内報、社内ポータルサイトなどを活用し、産業医が担当する職務(職場巡視、健康相談、衛生講話、メンタルヘルス対策など)について具体的に説明しましょう。
活動内容を定期的に共有する
安全衛生委員会の議事録や産業医からの職場環境改善提案を社内掲示板で共有したり、衛生講話の開催を事前に告知したりするなど、産業医の活動実績を定期的に発信します。これにより、産業医の貢献を従業員が実感できるようになります。
自己紹介やプロフィールを掲載する
産業医の顔写真や専門分野、趣味などを簡単なプロフィールとして掲載することで、親近感が湧き、心理的な距離を縮めることができます。
2. 相談の心理的ハードルを下げる
従業員が産業医への相談をためらう最大の理由は、「相談内容が会社に知られてしまうのではないか」という不安です。この不安を解消し、安心して相談できる仕組みを整えることが重要です。
守秘義務の徹底を周知する
産業医には医師としての守秘義務があることを明確に伝え、面談で話した内容が本人の同意なく会社に共有されることはない、と繰り返し強調しましょう。
相談方法の選択肢を増やす
直接対面での相談だけでなく、オンライン面談やメールでの相談など、従業員が相談しやすい方法を複数用意します。
3. 従業員自身の健康リテラシーを高める
産業医は、従業員一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、主体的に行動することをサポートする存在です。従業員の健康リテラシーを高めることで、産業医との連携もよりスムーズになります。
健康セミナーや衛生講話を開催する
産業医の専門性を活かし、生活習慣病予防、ストレスマネジメント、睡眠の質向上など、従業員が関心を持つテーマで定期的にセミナーを開催しましょう。
健康情報の発信
産業医の監修のもと、季節ごとの健康情報や最新の医療情報を社内報やメールで発信することで、従業員が健康に関する知識を自然と身につけられる環境を構築します。
これらの働きかけを通じて、産業医と従業員の間に信頼関係が生まれ、従業員は困ったときに自ら産業医に助けを求めるようになります。これにより、産業医は単なる「法律上の義務」ではなく、従業員の心身の健康を支え、企業の生産性向上に貢献する真のパートナーとなるでしょう。
まとめ
「産業医が役立たず」と感じる背景には、専門性やコミュニケーション不足、会社への関与の薄さ、契約内容と期待値のミスマッチ、そして産業医の役割への理解不足が主な原因として挙げられます。しかし、これらの課題は、適切な産業医の選び方と効果的な付き合い方によって解決可能です。
本記事で解説したように、求める役割を明確にし、事前面談で相性を確認し、定期的な情報共有と連携を密にすることで、産業医は企業の健康経営を力強くサポートする存在となります。
それでも、現在の産業医との関係改善が難しいと感じた場合は、そもそも最初の「選び方」を見直す必要があるかもしれません。
この記事の要点
- 産業医が「役立たず」と感じられる主な原因は、専門性のミスマッチ、コミュニケーション不足、会社への関与の薄さ、契約内容と期待値のギャップ、そして会社側の産業医への理解不足の5つに集約される。
- 産業医の専門性を最大限に活かすためには、契約前に自社が求めるスキルや専門分野を明確にし、その実績を詳細に確認することが重要である。
- 産業医との円滑な連携には、定期的な情報共有の場を設けることが不可欠である。
- 職場巡視や安全衛生委員会への参加を形骸化させず、具体的な目的を共有することで、産業医が企業の健康課題に深く関与するよう促せる。
- 契約内容と期待値のズレを防ぐため、契約前に業務範囲や対応頻度などを詳細に定義し、定期的に契約内容を見直す必要がある。
- 産業医の役割や法的義務を会社側が正しく理解し、従業員への守秘義務の周知や相談しやすい環境を整えることが、産業医を最大限に活用する鍵となる。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- ご要望をヒアリングし嘱託産業医を紹介
- 産業医と会社と従業員を“つなぐ”サービスを提案
自社に最適の産業医を
お探しの企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!