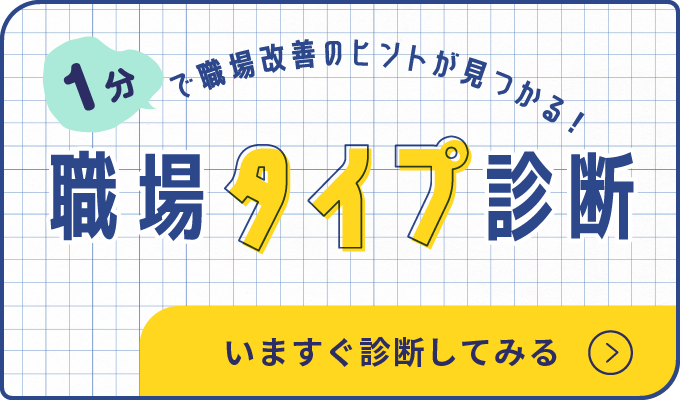法定休暇の取得率を上げる方法 有給・育休・介護休暇を活かす制度設計と職場の風土づくりについて
2025.11.10

制度は充実していても、実際には休みを取りづらい――。多くの企業で起きているこのギャップは、周知不足だけでなく、制度設計と職場風土に原因があります。本記事では、人事・総務がすぐに着手できる対策に絞って、年休の年5日取得義務を確実に満たしつつ、有給・育休・介護休暇を“使える制度”へ変える方法を解説します。
目次
休暇が“使われない”職場の背景と改善策
法定休暇制度の利用が進まない背景には、次の問題があります。これらは、単なる制度の周知不足以上の、根深い組織的な問題です。この根本原因を理解し、次のような対策を講じることが、取得率向上への鍵となります。
1.従業員の心理的障壁:管理職の「休まない姿勢」と負い目
休暇取得に対する最大の障壁は、従業員が「周りに迷惑をかける」「評価が下がるのではないか」と感じる心理的なプレッシャーです。特に、現場を統括する管理職が多忙を理由に休まない姿勢を見せると、「自分も休めない」という無言の圧力が組織全体に広がります。
【対策】管理職自身の率先した休暇取得の義務化と可視化
管理職が部下に休暇取得を促す最も有効な方法は、管理職自身が年休や法定休暇を計画的に取得し、その姿を部下に明確に示すことです。経営層は、管理職が年休取得を諦めることがないよう、管理職層の業務負荷軽減と業務バッファ確保を支援する責任を負います。管理職が「休める」環境にあることを可視化することで、「自分も休んでいい」という、「休みやすい空気」を作ることができます。
【対策】経営層のコミットメントとメッセージ発信
経営層が法定休暇の重要性を全社に繰り返し発信し、「制度利用は従業員の権利であり、会社として全面的に支持する」という明確なメッセージを打ち出します。これにより、制度利用に伴う心理的な負い目を取り除きます。
2.現場の組織的課題:人手不足と属人化への実効的な対応
人手不足の現場では、「業務の属人化」が常態化し、休暇取得を前提とした体制づくりが最重要課題となります。
【対策】休暇取得を前提とした「バッファ」のある勤務体制の構築
属人化の解消を短期で実現できなくても、まずは「休暇取得によって業務が止まらないこと」を最優先の目標とします。年休や法定休暇の利用実績を基に、全業務に対して10%程度の「予備工数(バッファ)」を見込んだ業務計画を立てます。このバッファを、引継ぎや情報共有、突発的な業務の代行時間として活用することで、休暇取得を前提とした組織の柔軟性を確保します。
【対策】情報共有の「必要十分条件」のテンプレート化
業務の完全なマニュアル化が難しい現場に合わせ、「休む際に最低限共有すべき情報」のテンプレート化に焦点を絞ります。
- 引継ぎ先と連絡先の明記:業務連絡先のリスト化と、引継ぎを依頼したメンバーの明記。
- 進捗状況の可視化の義務付け:進行中のタスクの進捗状況を、共有ツール(クラウド上のタスクボードなど)で常に最新の状態にしておくことを義務付ける。
- アクセス権限の確保:担当者不在時に必要なファイルやシステムへのアクセス権限を事前にチーム内で設定・共有しておく。
これにより、「誰が、どこに、どの情報を残せば、他のメンバーが困らないか」という必要最低限の情報共有のハードルを下げることで、休暇取得の心理的障壁を解消します。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせる法定休暇の取得率を上げるためにできる対策
法定休暇制度を単に「法律通り」に運用するだけでなく、従業員が「使いやすい」と感じるよう、一歩踏み込んだ制度設計を行うことが、取得率向上の決め手となります。
1.戦略的な年次有給休暇の取得促進と利用の柔軟化
年次有給休暇(年休)は、労働基準法で年5日の取得が義務化されていますが、単に取得させるだけでなく、その利用の柔軟性を高めることが重要です。
- 計画的付与制度の活用と義務遵守の管理:会社全体や部門単位で年休の計画的付与制度を導入し、全従業員が確実に休みを取る日を設けます。管理職は部下全員の年休取得状況を常にモニタリングし、法定義務である年5日の確実な取得を計画的に推進する責任を負います。
- 時間単位年休の導入と周知:年休を半日単位ではなく時間単位(1時間単位など)で取得可能にします。これにより、「役所への手続きの2時間だけ」「子どもの面談の1時間だけ」といった細やかなニーズに対応できるようになり、年休をより有効かつ効率的に利用できます。
2.子の看護休暇・介護休暇の有給化や利用しやすさの向上
子の看護休暇や介護休暇は、突発的な事態に対応するためのセーフティネットです。これらの休暇が取得しにくいと、従業員は、年次有給休暇を緊急時対応に充ててしまい、年休が本来の目的(心身の回復やリフレッシュ)に使われません。
- 無給休暇の有給化:法定では無給ですが、企業独自の規定としてこれらの休暇を有給化します。特に介護の初期段階や急な病状悪化の対応は精神的・経済的負担が大きいため、有給化は従業員の安心感を高め、年休を本来のリフレッシュ目的のために温存できる戦略的な措置となります。一方で、これらの休暇を有給化することは、利用しない従業員にとって不公平に映る可能性があります。不公平感を和らげるためには、この種の特別休暇を「セルフケア休暇」や「ウェルネス休暇」などとし、誰もがとれる休暇制度へと変えることなども検討しましょう。
- 時間単位取得の全面的な導入:年休と同様に、これらの休暇も時間単位での取得を可能にします。これにより、「通院の付き添いの2時間だけ」「デイサービスの送迎時間だけ」といった柔軟な対応が可能となり、制度の実効性が格段に向上します。
3.生理休暇の取得推進と産業保健スタッフの連携
生理休暇は女性の健康に直結しますが、「生理休暇」という直接的な名称が心理的障壁となり、取得を妨げます。活用しやすくするためには、従来の「生理休暇」という名称を、女性のライフステージ全般の健康課題を包括するインクルーシブな名称(「エフ休暇(F休暇)」「ウェルネス休暇」など)に変更したり、理由の詳細を問わず、上長への簡潔な連絡(メールやチャットなど)のみで申請できるようにするといった工夫が必要です。 また、制度の周知と同時に、女性特有の健康問題に関する産業保健スタッフ(産業医、保健師、助産師など)によるセミナーを定期的に実施します。
法定休暇を“使える制度”にするための職場づくり
制度を設計するだけでなく、それが全従業員にとって「当たり前の選択肢」となるよう、企業風土を根本から変革する必要があります。
1.管理職が率先して休む文化の定着
先に述べたように、管理職自身の休暇取得は、制度運用の鍵です。ここでは、それを組織文化として定着させるための具体策を紹介します。
- 管理職自身の休暇取得の徹底と可視化:管理職自身が有給休暇や法定休暇を積極的に取得し、部下に対して「休むことはプロセスの見直しと業務効率を上げるために必要だ」という姿勢を体現します。
- 休暇取得の推奨を日常業務に:管理職が部下に対して、計画的な休暇の取得を日常的に推奨する習慣を定着させます。期末や繁忙期前に、残りの年休を確認し、取得計画を立てさせるなどの具体的なアクションが有効です。
2.「お互い様」で支え合う職場風土の醸成
育児や介護など、ライフイベントによる制約は、誰もが直面する可能性のあることです。多様な働き方を「特別」とせず、互いにサポートし合う文化が必要です。
- ダイバーシティ研修の実施:育児や介護がキャリアに与える影響、多様な働き方を理解するための「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」などの研修を全従業員に実施します。
- チーム内での業務共有会議の定例化:従業員の誰かが休暇を取ることを前提とした業務共有とバックアップ体制の確認会議を定例化します。これにより、休暇を取得する本人だけでなく、チーム全体が責任を持ってサポート体制を構築する意識が根付きます。
3.制度運用を定期的に見直す仕組み
制度が実際に機能しているかを定期的にチェックし、改善に繋げるPDCAサイクルを回します。
- 取得率の部門別・性別比較:休暇制度の取得率を部門別、性別、職種別に分析し、取得率が低い部門の管理職に対しては、原因究明と改善計画の提出を求めます。
- 匿名アンケートの実施:制度利用者や非利用者に対して、「制度利用をためらった理由」「申請時に感じたストレス」などを尋ねる匿名のアンケートを定期的に実施し、制度設計や風土改善のための具体的なデータとして活用します。
まとめ
法定休暇を「使える制度」として定着させることは、企業が単に法令を遵守するだけでなく、従業員の働きやすさを本気で考えている証にもなります。制度の「箱」を整えるだけでなく、それを支える「空気」を作るためには、管理職の意識改革と、休暇取得を前提とした勤務体制の構築という、組織的な課題に立ち向かう必要があります。これは、自社の人事・総務部門だけで実現するには困難な課題です。
もこすく相談所では、法定休暇の取得を阻む組織的な課題を分析し、保健師や助産師をはじめとする産業保健のプロが、従業員の心身の健康への配慮を含めた最適な制度設計と、風土醸成のための具体的な施策(研修、面談フローの構築など)を提案します。
「制度はあるのに使われない」というお悩みを解決し、優秀な人材が安心して働き続けられる環境を実現するために、ぜひご相談ください。
この記事の要点
- 法定休暇の取得率を上げるためには、管理職自身が年休を計画的に取得し、その姿勢を可視化することで、「休める」企業風土を組織のトップダウンで醸成することが重要
- 業務計画に予備工数(バッファ)を設け、休暇取得によって業務が止まらないための時間的余裕を確保する必要がある。
- 男性が育休を取得し実践することで、職場の休暇に対する寛容性が向上し、女性従業員も心理的な負い目なく休みやすくなる。
- 子の看護休暇や介護休暇を有給化し、時間単位で取得可能にすることで、緊急時の対応のために年休が消費されるのを防ぎ、制度の実効性を高める。
- 生理休暇の名称を変更したり、PMSや更年期不調に適用範囲を広げることで、心理的抵抗を解消する。
- 完全なマニュアル化が難しくても、休む際に必要な引継ぎ先、進捗状況、アクセス権限を簡潔に共有する仕組みを義務付け、現場の負担を最小限に抑える。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- 内部通報窓口を完備
- 女性の一生をケア・サポートする助産師が対応
- 会社と従業員を“つなぐ”サービスを提案
- 男性も相談できる
女性が働きやすい会社を
実現したい企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!