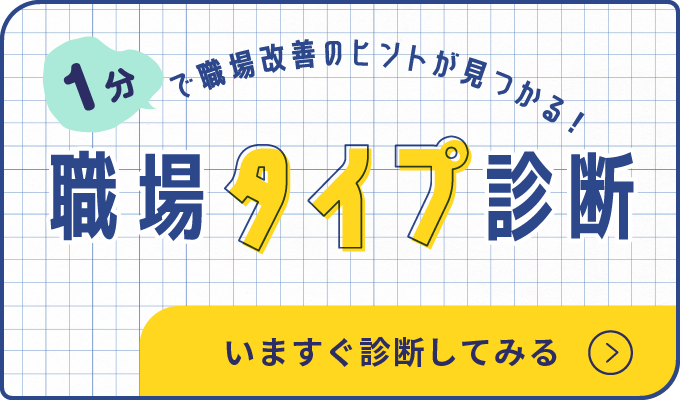ストレスチェックの報告書作成について 労基署への提出書類と衛生委員会での報告内容を解説
2025.11.03

ストレスチェックは、実施して終わりではありません。本当に大切なのは、その結果を活かして、職場改善につなげていくことです。そのために重要なのが、適切な報告書の作成です。労働基準監督署へ提出する報告書は義務のためもちろん重要ですが、ストレスチェックを有効活用するには、社内で活用するための報告書も工夫して作成する必要があります。では、どのような内容を記載すればよいのでしょうか。
この記事では、ストレスチェック後に必ず行うべき報告書作成と提出の基本から、衛生委員会で効果的に報告・活用するためのポイントまでを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
法定報告書作成の基本:必須事項と提出方法
従業員50人以上の企業において、ストレスチェックが終了したら、まず法定の手続きとして、所轄の労働基準監督署へ報告書を提出する義務が発生します。「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を作成し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。これは、労働安全衛生規則第52条の21に基づく、労働安全衛生法上の義務です。
提出の期限は、ストレスチェック終了後、概ね1ヶ月以内が目安とされています。提出を怠った場合、労働安全衛生法第120条第5号に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただし、法定報告書の作成はそれほど煩雑な業務ではありません。外部委託業者やシステムから提供される集計データ(受検率、高ストレス率、面接指導実施率など)を整理し、労働基準監督署提出用の法定報告書のフォーマットに入力転記すれば問題ないためです。この作業は、正確性が求められる実施事務従事者の業務です。なお、外部委託業者によっては、提出用の報告書の作成も可能です。
報告書に記載すべき必須項目
ストレスチェック結果報告書は、厚生労働省が定めるテンプレート(様式)に沿って作成する必要があります。
報告書に個人の検査結果を記載する必要はありませんが、以下の集計結果を正確に記載することが必須です。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 事業場情報 | 事業場の名称、所在地、業種、在籍労働者数など |
| 実施体制 | 検査実施月、実施者および面接指導を実施した医師について |
| 検査結果 | 受検者数、面接を受けた人数 |
| 集団分析 | 集団分析の実施の有無 |
報告書は、企業がストレスチェックを適正に実施したことを示す証明書のようなものです。正確なデータに基づいて、必須項目を漏れなく記載することが重要です。
報告書の提出方法
以前は郵送や窓口への提出が求められていましたが、2025年1月より電子申請での提出が義務化されています※。
『e-Gov(イーガブ)電子申請』から提出することができます。
こちらを利用することで、ストレスチェック報告書の入力作業から提出までの作業がオンラインで完了します。
また、(「労働安全衛生法関係の
届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用すると、オンラインで帳票作成もできます。)
※参考:厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されます」
衛生委員会での報告と「集団分析結果」の活用
労働基準監督署への報告は義務ですが、ストレスチェックの結果を有効活用するためには、その結果に基づいた「職場環境改善」について議論し、改善案を実施することで初めて、ストレスチェックを有効活用することができます。ここでは、担当者の負荷を軽減しつつ、議論をスムーズに進めるための報告書作成・報告手順を紹介します。
1. データ集計と整理
まずは、外部委託業者やシステムから提供される集計データ(受検率、高ストレス率、面接指導実施率など)を整理します。
2. 集団分析結果に基づく「課題の可視化」
衛生委員会での報告資料には、法定報告書の内容に加えて集団分析の結果も掲載することが望ましいです。部署や職種ごとのストレス傾向や要因(仕事のコントロール量、同僚や上司の支援など)を可視化した集団分析結果を報告することで、職場改善に向けた議論がしやすくなるためです。
ただし、集団分析の結果をそのまま共有するだけでは、具体的な議論が進まない可能性があります。そこで人事・総務の担当者は、報告の際に「どの集団で、どんなストレス要因が強いか」を具体的に議論できるように、事前に整理しておくことが重要です。そのためにまずは、所属・職種・雇用形態別など、様々な角度で集団分析を行っておくようにしましょう。
さらに、報告書を作成する段階で次のような工夫をしてみましょう。
- ● 所属や性別、年代、雇用形態などによる結果の違いが一目で分かるようにしておく
- ● 全国平均と比較して、自社のメンタルヘルス状況を相対的に判断できるようにする
- ● 時期的な要因や、継続的な問題点の有無を把握するために、前年度のデータと比較する
- ● 労働時間・休暇取得状況やエンゲージメントに関するアンケート結果など、ストレスチェック以外の従業員に関するデータを併せて可視化する
このような工夫をしておくと、報告書がより分かりやすくなり、衛生委員会でもスムーズに議論に入ることができるようになるでしょう。
なお、集団分析は管理職の責任を問うために行われるものではありません。
「労働者の健康を守り、会社を発展させるために実施する」ものであり、この目的を明確に発信することで、会社全体がストレスチェックに前向きに取組めるようになります。
3. 実施者(医師・保健師など)による専門的意見の添付
集団分析の結果を提出する際には、実施者である産業医や保健師からの専門的な見解や解釈を添えると良いでしょう。たとえば、「この部署のストレスが高いのは、長時間労働よりも上司の支援不足に起因する可能性が高い」「高ストレス者の面接指導勧奨に対する拒否率が高い原因は、情報管理への懸念にある」といった、具体的な意見を入れることで、委員会での議論がより具体的になり、改善施策に繋がりやすくなります。
ストレスチェックの報告書作成を外注するメリット
「多忙で報告書作成に時間をかけられない」「集団分析の結果をどう解釈していいか分からない」という不安がある場合は、報告書作成業務も依頼できる外部委託の検討をおすすめします。 詳細な報告書の作成を外部に任せることで、実務担当者の負担が軽減され、報告書の質も高めることができます。
具体的には次のメリットがあります。
ミスのリスクが減らせる
外部業者が提供するフォーマットは、法定の必須項目を漏れなく、正確な形式で作成されているため、記入漏れのリスクを回避できます。
専門的な考察が得られる
産業保健のプロの視点から、集団分析結果の解釈と具体的な施策の提案を含めた報告書が作成できるため、実務担当者の考察負担を大幅に軽減できます。これが最大のメリットです。
職場改善案に向けた次の一歩が踏み出せる
業者によっては、産業医・保健師の派遣や、詳細な報告資料の作成支援、衛生委員会での出席と報告などを行っているところもあります。こうしたサービスの利用は、職場改善に向けた取り組みに繋がります。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせるストレスチェック報告書を有効活用するための業者の選び方
ストレスチェックを職場改善に結びつけるには、業者選びも重要なポイントです。 たとえば、社内の産業医が実施者を務めている場合でも、集団分析や職場改善まで踏み込んだサポートを受けられないケースもあります。 そうした場合には、単なる集計代行ではなく、詳細な報告書の作成や改善提案までサポートしてくれる業者を選ぶのが理想です。
委託先を選ぶ際には、以下の点をチェックしましょう。
-
● 集団分析や報告書作成に強いか
法定報告だけでなく、職場改善につながる具体的な提案ができるかを確認。 -
● 産業医・保健師との連携体制があるか
自社で選任している専門職とスムーズに連携できるかどうかが重要。 -
● 報告書の見やすさ・わかりやすさ
グラフやチャートなど、衛生委員会で共有しやすい形式かどうかを事前にサンプルで確認。 -
● サポート範囲と対応スピード
提出期限に間に合うスケジュール感や、報告会での立ち会いなど、対応範囲を明確にしておく。 -
● 専門的な考察や助言が含まれているか
データの“読み取り”までを含めたサービスであれば、衛生委員会報告の質が格段に上がる。
報告書作成サービスを利用する際は、単なる事務代行ではなく「職場改善への投資」と考えることが大切です。 丁寧に作られた報告書と専門家のサポートがあれば、ストレスチェックの結果を次のアクションへと確実につなげることができます。
まとめ
本記事では、ストレスチェック後の報告書作成の義務と、衛生委員会・社内報告の重要性や、報告書作成を外部に委託するメリットを解説しました。効果的なストレスチェックを実施するために最も重要なのは、報告書を単なる「提出義務」で終わらせず、集団分析の結果を「職場改善の土台」として活用することです。そのためには、法定報告書の作成と衛生委員会資料の作成、そして産業医からの専門的意見の取りまとめといった手間のかかる実務を、いかに正確かつ効率的に行うかが鍵となります。 「報告書作成や委員会報告に不安がある」「集団分析の結果を施策に繋げられない」といったお悩みがある場合は、無理をせず外部の業者に依頼しましょう。
ストレスチェックにはゴールはありません。
よりよい職場づくりを成功させるためには継続的な取り組みが大切です。
もこすく相談所では、法定報告書の作成支援、集団分析結果の専門的な考察、さらには衛生委員会での産業医・保健師の報告サポート・専門家派遣まで、包括的に支援いたします。 まずは、貴社が抱える報告書作成や委員会運営に関する具体的な課題について、お気軽にご相談ください。
この記事の要点
- ストレスチェック実施後、企業には労働基準監督署への法定報告書提出義務(概ね1ヶ月以内)がある。
- 法定報告に加え、衛生委員会での報告も重要で、集団分析の結果を基に職場改善の議論を行うために必要不可欠なプロセスである。
- 委員会で結果を活かすには、実施者(産業医・保健師など)による専門的な考察や意見を添付し、改善施策案を明確にすることが成功のコツ。
- 報告書作成や委員会報告に不安がある場合は、外部委託により法令遵守の確実性、専門的な考察、担当者の負担軽減といったメリットが得られる。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- 御社に合ったストレスチェックをご提案
- 包括的なメンタルヘルス対策で離職防止につなげる
ストレスチェックを
有効活用したい企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!