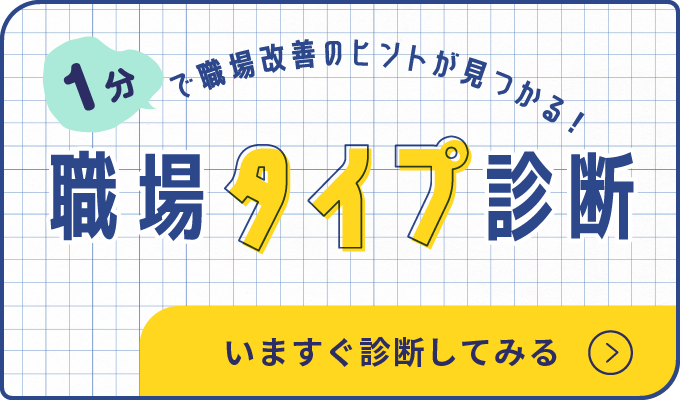ストレスチェックの集団分析で何がわかる?職場環境改善に活かすメリットと活用方法
2025.10.16

毎年実施されるストレスチェックは、従業員の心身の不調を早期に把握し、職場全体の心の健康を支え、企業全体のパフォーマンスを向上させるための重要な取り組みです。中でも、ストレスチェック結果を組織単位でまとめる「集団分析」は、法律上は努力義務とされていますが、職場の現状を客観的に把握し、今後の改善につなげるために欠かせません。とは言え、「結果を見ても、活用方法が思い浮かばない」「集計はしたものの、職場改善に結びつかない」と感じる担当者も少なくありません。そこでこの記事では、集団分析で明らかにできる内容や、実務での活用ポイントについて解説します。集団分析の活用方法を知って、従業員が安心して働ける環境づくりに取り組みましょう。
目次
ストレスチェックの集団分析の特徴や分かること
はじめに、集団分析の特徴や分かることをご紹介します。
1. 個人を特定せずに、職場ごとの特徴を把握できる
集団分析は、部署・職種・年代別など一定規模のグループで集計します。これにより、個人を特定せずに、どの職場でどのような要因によるストレスが高いのかを明らかにできます。個人が特定されないよう、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」では、原則として10人を下限の人数としています。また、この10人は在籍労働者数(対象者数)ではなく、実際の受験者数であることにも注意しましょう。
2. 「仕事のストレス判定図」でリスクを可視化
厚生労働省が推奨する「仕事のストレス判定図」では、職場のストレス状況を2つの視点から評価します。代表的なものは以下の通りです。
| 判定図の種類 | 内容 | 明らかになる課題 |
|---|---|---|
| 量-コントロール判定図 | 仕事の量的負担と、裁量のバランス | 負担が大きく裁量が少ない職場では、燃え尽き症候群やメンタル不調のリスクが高まる傾向があります。 |
| 職場の支援判定図 | 上司や同僚からのサポート状況 | 支援が不足している職場では、孤立感や人間関係に起因するストレスが高まりやすくなります。 |
.png)
3. 「総合健康リスク」で全国平均との比較ができる
集団分析では、全国平均と比較して自社のストレスリスクがどの程度かを示す「総合健康リスク」が算出されます。この指標により、自社の職場環境が他社と比べてどの位置にあるのかを客観的に把握することができます。
4. 経年比較で施策の効果を確認できる
ストレスチェックは毎年実施するため、前年との比較が可能です。これにより、昨年実施した施策(残業対策、管理職研修など)の効果を数値で検証できます。データに基づいた改善のサイクルを確立するうえで重要なポイントです。
ストレスチェックで集団分析を実施する3つのメリット
努力義務とはいえ、集団分析を行うことで得られる経営的なメリットは少なくありません。ここでは3つのメリットを紹介します。
1.職場改善の優先順位を明確にできる
全社的に一律の対策を行うことも重要ですが、時間や予算が限られている場合は、データに基づいて重点的に取り組む部署を絞る必要があります。たとえば、以下のようにデータを根拠とした施策立案が可能になります。
- ● 高ストレス傾向が強い部署や年齢層に重点施策を実施
- ● 「人間関係」の課題が多い部署ではコミュニケーション研修を実施
- ● 「コントロール感」が低い職場では権限移譲などを検討
2. 離職防止・生産性向上につながる
高ストレスの状態を放置すると、休職・離職の増加や、生産性の低下(プレゼンティズム)を招く恐れがあります。集団分析の結果を活かすことで、こうした兆候を早期に把握し、対策を講じることができます。
3. 経営層への説明材料として活用できる
集団分析の結果は、「なんとなく不調者が多い」といった感覚的な課題を、数値として示す客観的な根拠になります。これにより、経営層に対してメンタルヘルス対策や組織改善施策の必要性を説得力をもって説明できます。また、毎年の分析結果を蓄積することで、PDCAサイクルを回す仕組みを構築することも可能です。
ストレスチェックの集団分析結果はどう読み解けばいい?
集団分析結果を見ても、「判定図やグラフはあるけれど、どう読み取ればいいのか分からない」という声は少なくありません。ここでは、結果を見る際に押さえておきたい基本的な視点を整理します。
1.数値の「高い・低い」だけで判断しない
集団分析の結果は、平均値の上下だけで一喜一憂するものではありません。重要なのは、職場ごとの特徴や変化の傾向を読み取ることです。たとえば、全体的には良好でも、ある部署や年代だけ数値が悪化している場合には、その集団に特有の要因がある可能性があります。一方で、前年より改善している部署があれば、その要因を職場全体の好事例として共有することも有効です。
2.「仕事量」と「裁量(コントロール)」のバランスを見る
ストレスチェックの「量−コントロール判定図」では、仕事の負担と裁量の関係性が分かります。負担が大きく裁量が小さい職場では、疲労や不満が溜まりやすく、改善の優先度が高いと考えられます。一方で、負担が高くても裁量が十分にある場合は、「忙しいけれどやりがいがある」状態かもしれません。こうした読み取り方をすることで、単純な数値比較では見えない職場の特徴が見えてきます。
3.「支援の状況」はストレス度合いを左右する
上司や同僚からの支援が不足している職場では、同じ仕事量でもストレスが高く出やすくなります。「職場の支援判定図」で支援のスコアが低い場合は、人間関係や相談のしやすさに課題がないかを確認してみましょう。特にリモートワークなど、顔を合わせる機会が少ない環境では、支援の感じ方に差が出やすい傾向があります。
4.数値の背後にある「背景」を考える
数値の変化には必ず理由があります。業務量の増加、組織変更、繁忙期など、外的な要因が影響している場合も多くあります。「どの時期に」「どんな出来事があったか」といった背景を踏まえると、データの意味がより具体的に理解できます。単に「上がった」「下がった」と捉えるのではなく、変化の理由を一緒に探ることが大切です。
5.迷ったときは、専門家の視点を取り入れる
数値の読み取りや解釈に迷うときは、産業医や保健師、心理相談員などの専門家に相談するのがおすすめです。専門家が関わることで、単なるデータの確認に留まらず、「この結果を踏まえて、何をすればよいか」という次の行動指針を整理することができます。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせるストレスチェックの集団分析を職場改善に活かすポイント
集団分析の結果を読み取ったら、次に重要なのは、どう行動に移すかです。ここでは、分析結果を実際の職場改善に結びつけるための進め方を紹介します。
1. 結果を分析し、職場全体の課題を確認する
集団分析の結果を全社員に無制限に共有することは不適切です。共有する範囲や利用方法については、あらかじめ衛生委員会等で協議しておく必要があります。 その際、個人が特定されないように十分配慮しつつ、職場全体としてどんな傾向があるのかを客観的に伝えることを意識しましょう。「結果を開示すること=問題の指摘」ではなく、「改善のための現状把握」であることを明確にすると、受け取る側の納得感も高まります。
2. 「データ」と「現場の声」をあわせて考える
集団分析のデータは、客観的な数値情報です。一方で、実際の職場には「なぜその結果になったのか」という背景があります。分析結果をもとに、該当する部署やチームにヒアリングや意見交換を行うことで、課題の根本原因が見えやすくなります。 たとえば、「上司の支援が少ない」と出た場合、一見すると上司が部下への気配りが足りなく、冷たいような印象を与えますが、現場の声を聞いてみると、上司はとても良い人だが、上司自身の業務量が多くて、部下のサポートに手が回っていない、ということが分かることもあります。このような場合は、上司に対して管理職研修をすることよりも、上司自身の業務負担を軽くする取り組みを考えるほうが、効果的です。 このように、データと現場の実感を組み合わせることで、より実態に即した改善策を立てられます。
3. 優先順位をつけて小さなことから始める
職場改善の取り組みは、一度にすべてを行う必要はありません。まずは、負担が大きい部署やストレスの高い集団など、影響の大きい部分から着手しましょう。取り組みの成果が出ることで、他の部署にも「自分たちでもできる」という意識が広がり、改善活動が定着しやすくなります。
- ● 例:残業が多い部署 → 業務分担の見直し
- ● 例:支援が不足している部署 → 管理職研修・1on1導入
- ● 例:ストレス要因が曖昧 → 定期的なアンケート・面談実施
「どこから始めるべきか分からない」「何を優先すればよいか迷う」というときは、産業医や産業保健スタッフなど、第三者の視点で整理してもらうのも効果的です。
4. 専門家と連携し、PDCAを回す
集団分析の結果を継続的に活かすためには、毎年の結果を比較・検証し、改善の効果を確認することが重要です。この「分析→改善→検証」のサイクルを安定して回すためには、専門家のサポートが欠かせません。 産業医・保健師などの専門家が関与することで、数値の背景にある心理的要因や職場構造の問題を客観的に分析できる、改善策の効果を定量的に測定できる、経営層への報告書や提案資料の説得力が高まる、といったメリットがあります。
もこすく相談所では、集団分析の結果をもとに、専門スタッフが職場ごとの課題整理・施策提案・効果検証を支援しています。「結果を見ても次のステップが決められない」「改善の方向性を整理したい」という場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
ストレスチェックの集団分析は、職場の現状を見える化し、改善の方向性を示すための大切なステップです。結果を正しく読み取り、専門家のサポートを得ながら具体的な施策に落とし込むことで、従業員が安心して働ける職場環境づくりに活かせます。
もこすく相談所では、集団分析結果の考察や職場改善のサポート、産業保健スタッフの派遣など、分析から改善まで一貫した支援を行っています。ストレスチェックを有効活用したいご担当者様はぜひお問い合わせください。
この記事のポイント
- 集団分析は、個人を特定せずに職場ごとのストレス傾向を可視化できる仕組みである。
- 「仕事のストレス判定図」などを活用すると、負担・裁量・支援のバランスを客観的に把握できる。
- 数値の変化だけでなく、その背景を読み解くことで、実態に即した課題を見つけられる。
- 結果は関係者で共有し、現場の声と合わせて具体的な改善策を検討することが重要である。
- 専門家と連携して継続的に取り組むことで、職場環境の改善と定着を図ることができる。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- 御社に合ったストレスチェックをご提案
- 包括的なメンタルヘルス対策で離職防止につなげる
ストレスチェックを
有効活用したい企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!