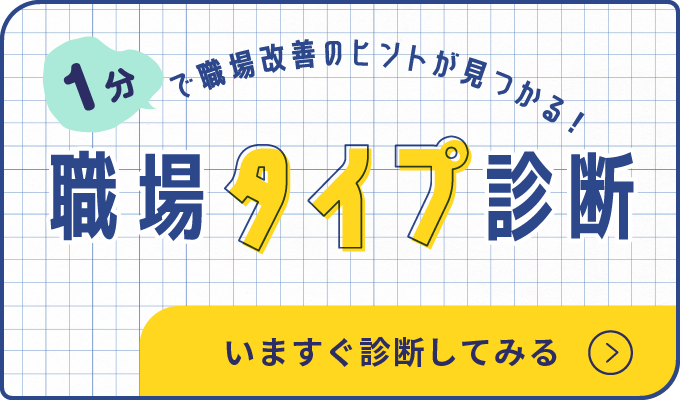ストレスチェックの「実施者」と「実施事務従事者」の選び方、役割分担について解説
2025.10.15

ストレスチェック制度は、多くの企業で毎年行われる大切な取り組みです。現在は、従業員数が50名以上の事業場のみに実施が義務付けられていますが、今後は、50名未満の事業場も、義務化される可能性があります。
実際にストレスチェックを実施することになり、まず問題になるのが、「誰が担当するか」という点です。ストレスチェックの中核を担うのは、「実施者」と「実施事務従事者」です。では、この2つはどう違うのでしょうか。また、誰に何を任せればいいのでしょうか。
この記事では、ストレスチェックの実施体制を整えるうえで知っておきたい、実施者と実施事務従事者の違いと選び方について、分かりやすく整理して解説します。社内リソースで対応できない場合の対策も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
実施者の資格要件と役割
ストレスチェック制度において、実施者は制度の中核を担う専門家です。実施者は誰でもなれるわけではなく、以下の専門的な資格を有する者に限られています。
- ● 医師
- ● 保健師
- ● 厚生労働大臣が定める研修の修了など、一定の条件を満たした看護師または精神保健福祉士、歯科医師、公認心理士
多くの企業では、日頃から労働者の健康管理に携わっている産業医や保健師、看護師などが、実施者となるケースが一般的です。
このように実施者が特定の有資格者に限定されているのは、単にストレスチェックを「実施するだけ」ではなく、専門的な視点から制度全体を支える役割が求められているためです。たとえば、ストレスチェックの内容をどう設計するか、どの調査票を使うか、結果をどう評価するか、高ストレス者をどう判定するか――といった重要な判断を担うのも実施者です。これらは専門知識や専門の資格を持たない人には対応できない領域です。
そして、実施者が負う責任の中で特に重要なのが「守秘義務」を守ることです。医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理士は、様々な法律によって、守秘義務が課せられています。そのため、業務上知り得た個人の健康情報を、本人の同意なく事業者や他の人に伝えることはできません。 こうした厳密な情報管理を制度において保証することで、従業員が安心してストレスチェックを受けられる環境が実現します。
実施事務従事者の役割
実施事務従事者は、実施者の指示のもと、ストレスチェックの事務的な作業を担当します。たとえば、調査票の配布・回収、専用システムの操作、データの集計、結果通知書の印刷・封入、外部機関との連絡調整などで、実施に関わる多くの工程を支えています。こうした業務を行う中で実施事務従事者は、高ストレス者の情報や面接指導に関する手続きなど、センシティブな情報を取り扱うことになります。
ところが、実施事務従事者には、実施者のような法的な資格要件は定められていません。そのため、人事に権限を持つ管理職などでなければ、基本的には誰でもなることができますが、実施事務従事者には労働安全衛生法において守秘義務が発生します。そして、違反した場合の罰則も規定されています。もし、実施事務従事者が知り得た高ストレス者の情報をうっかり、あるいは意図的に漏洩させてしまった場合、それは法令違反となり、従業員からの訴訟リスクや損害賠償に発展する可能性があります。
さらに、メンタルヘルスというデリケートな情報の管理体制が杜撰だと判明した場合、従業員全体の会社への信頼が著しく低下します。安全・確実なストレスチェックを実施するためには、実施事務従事者に対し、事前に守秘義務に関する誓約書を取り交わすなど、厳格な教育と管理体制を敷くことが不可欠です。
多くの場合、人事・労務担当者など、社内の職員が実施事務従事者の役割を担いますが、守秘義務を確実に守れる信頼性と、正確に業務を進める実務能力の両方を兼ね備えていることが求められます。
実施事務従事者の負担は大きいですが、従業員からの信頼を守り、ストレスチェックを安全かつ効果的に運用するためには、大切なポイントと言えます。
自社でやる?外部委託する?最適な「人選」の判断基準
お伝えしたように、実施者と実施事務従事者はストレスチェックの中核的な役割を担いますが、その負担は決して軽くなく、社内リソースで対応することができない企業も少なくありません。そのような場合に選択肢となるのが、外部委託です。
外部委託はコストがかかりますが、リソースがないのに社内で済ませようとすると、思わぬミスや法令違反が起きるリスクが高まります。そうならないためにも、自社リソースで対応できるのか、外部に委託したほうが良いのかを、適切に判断することがとても重要です。
そこで、社内リソースで対応できる場合と、外部に委託しほうがよい場合の判断基準をご紹介します。
1. 自社内のリソースで対応できるケース
以下の条件が揃っている企業は、社内体制のみでストレスチェックを実施できる可能性があります。
□産業医・保健師などが在籍している
普段から従業員の健康管理に携わる産業医や保健師がいる場合は、実施者を依頼できる場合が多く、専門家の確保はクリアできます。
□実施事務従事者を担うことができる人的リソースがある
事務作業の負荷(調査票の配布・回収、データ入力、結果の仕分け、実施者とのコミュニケーション・調整、面談の手配など)に対応できる時間的余裕がある場合は、社内リソースで対応できる可能性が高くなります。
□高度なセキュリティ管理体制が構築されている
従業員の結果データを保管する場所が物理的にもシステム的にも完全に隔離されており、事業者が閲覧できない仕組みが整っている場合は、社内リソースで対応しやすいでしょう。
2. 外部委託を強く推奨するべきケース
以下の条件に一つでも該当する場合は、外部委託を真剣に検討すべきです。
□社内に実施者(医師・保健師など)がいない
外部に委託して、資格要件を満たした実施者を速やかに選任してもらう必要があります。
□人事担当者が多忙で事務作業を抱えきれない
外部委託をすることで、実施事務従事者の実務負担が大幅に軽減する場合があります。
□従業員に中立性や安全性が保たれないと懸念されている
外部の第三者がデータ管理を行うことで、情報漏洩リスクを排除し、従業員の信頼を得られます。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせる外部委託のメリット・デメリットとは
ストレスチェックを外部委託することは、企業リスクの低減と従業員の信頼獲得に繋がる大きなメリットをもたらしますが、一方で、注意すべき点も存在します。ここでは、外部委託のメリットとデメリットを紹介します。
外部委託のメリット
中立性が担保され、受検者に安心感を持ってもらえる
従業員の中には、ストレスチェックの結果が人事評価に悪影響を与えるのではないか、と心配する人もいます。もちろん、ストレスチェックの結果によって、不利益が生じることは法律で禁じられていますが、外部の第三者が実施者や実施事務従事者を担うことで、より制度の中立性が強化されるため、従業員は安心して受検しやすくなります。その結果、受検率が向上し、忖度なしの結果を引き出すことにも繋がります。
専門の業者に頼むことで、法令遵守が徹底され、専門的知見を有効活用できる
ストレスチェックのプロセスは複雑で、思わぬミスが法令違反のリスクに直結します。専門の業者は、法令に則った適切なプロセス設計、高ストレス者の選定基準、結果の通知方法などを熟知しており、確実な法令遵守を実現します。また、集団分析結果を職場環境改善に繋げる具体的なノウハウといった、専門的知見を活用できる点も大きな利点です。
社内担当者の負担が軽減され、コア業務へ集中できる
煩雑なシステム設定、データ処理、結果通知書の発送といった手間のかかる事務作業(実施事務従事者の役割)から解放されます。担当者は、事後の面接指導調整や集団分析に基づく環境改善施策の検討といった、企業価値を高める本質的なコア業務に集中できるようになります。
社内リソースのみを使おうとすると、実施することで手一杯になってしまいますが、適切な業者に委託できると、担当者の業務負担は大幅に軽減されます。ストレスチェックを単なる義務の遂行から、職場改善の機会へと変えることもできるでしょう。
外部委託のデメリット
外部委託は万能ではありません。導入時には以下のデメリットが生じることがあります。ただし、適切な対策を講じることができれば、デメリットを解消することもできます。
コストが発生する
当然ながら、外部に委託することで費用が発生します。特に、実施者の代行だけでなく、集団分析や職場改善案の提案、産業医面談の手配なども依頼すると、コストは高くなります。
価格だけでなく、職場改善につながる提案内容やフォロー体制まで含めて比較検討します。
企業内の状況が伝わりにくい
外部の実施者や実施事務従事者は、各社の独自の企業文化、人事制度、部署ごとの人間関係などを把握していません。そのため、集団分析の結果や面談指導の意見が実情に合っていない、と感じられる場合があります。
委託契約を結ぶ前に、自社の課題や特殊な事情をしっかりと伝えましょう。また、実施後も、人事担当者と産業保健スタッフ(実施者)との会議を定期的に設けるなど、外部とのコミュニケーションを密に取る仕組みを構築することが重要です。
データ移行や準備に手間がかかる
初めて外部委託する場合、従業員データの提供やシステムの連携など、初期設定にある程度の手間と時間がかかることがあります。
委託先が、データ移行やシステムの初期設定において、どこまでサポートしてくれるかを事前に明確にしましょう。サポートが手厚い業者を選ぶことで、初期の負担を大幅に軽減できます。
まとめ
本記事では、実施者と実施事務従事者の役割や、自社対応と外部委託の判断基準などについて解説しました。 効果的なストレスチェックを実施するために最も重要なのは、実施者と実施事務従事者を適切に選んで、労働者に安心してもらえる環境を作ることです。選任ミスをしてしまうと、法令違反や従業員の不信感に直結するため、注意しましょう。 「自社に有資格者がいない(または頼めない)」「人事部門に負担をかけたくない」「情報漏洩が怖い」といった不安がある場合は、ぜひ外部の業者に委託することも検討してみてください。
もこすく相談所では、ストレスチェックの実施前から事後フォローまで、貴社に合わせた最適な体制をご提案いたします。実施者業務はもちろん、煩雑な実施事務従事者業務の一部代行や、産業医の紹介や連携まで、包括的にサポートいたします。 まずは、現在の貴社の体制に関する疑問や、抱えている不安について、お気軽にご相談ください。
この記事の要点
- ストレスチェック制度の中核を担うのは実施者と実施事務従事者であり、それぞれの役割と責任を正しく理解して人選することが重要である。
- 面談の主な目的は、従業員の心身の健康維持・増進と、企業による適切な就業上の配慮にある。
- 実施者になれるのは、医師・保健師、一定の条件を満たした看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理士など、法律で守秘義務が課せられている専門職に限られ、ストレスチェックの設計・評価・判定などを専門的に担う立場である。
- 実施事務従事者は実施者のような特定の資格要件はないが、調査票の管理やデータ処理など実務を支える重要な役割を持ち、守秘義務違反は法令違反となるため、信頼性と実務能力の両方を兼ね備えていることが求められる。
- 自社で対応する場合は、産業医や保健師の在籍、担当者の余力、セキュリティ体制などが整っていることが条件であり、対応が難しい場合は外部委託を検討すべきである。
- 外部委託には中立性や法令遵守、担当者の負担軽減といったメリットがある一方で、コストや準備負担といった課題もあるため、事前の打ち合わせやサポート体制の確認が重要である。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- 御社に合ったストレスチェックサービスをご提案
- 包括的なメンタルヘルス対策で離職防止につなげる
ストレスチェックを
有効活用したい企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!