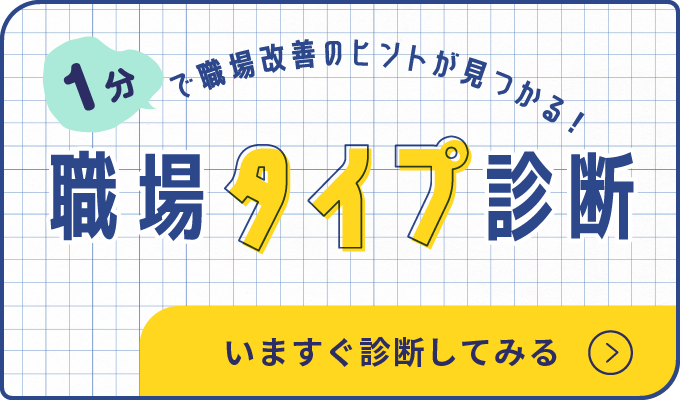ストレスチェック後の「高ストレス者」対応はどうすればいい?フローや注意点を解説
2025.10.15

毎年行うストレスチェック。無事に受検期間が完了しても、実務担当者にはまだやるべきことがあります。その一つが、「高ストレス者」への対応です。
高ストレス者への対応は、単に法令上の義務を果たすだけでなく、従業員のメンタルヘルスを守る最終防衛ラインであり、企業の安全配慮義務を果たす上で最も重要です。しかし、面接指導の実施には細かいルールもあり、難しく感じる方もたくさんいます。そこでこの記事では、ストレスチェック後の高ストレス者対応について、実務担当者が知っておくべき法定の対応フローと、面談勧奨のポイントなどを徹底解説します。
法令遵守と従業員の安全を守るためにも、この複雑な事後対応をどのように進めるべきか、確認していきましょう。
目次
ストレス者対応の法定フローと面談勧奨の手順
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員から面接指導の申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
以下のステップを順序通りに進めましょう。
ストレス者対応の法定フローと面談勧奨の手順
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員から面接指導の申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。以下のステップを順序通りに進めましょう。
-
STEP 1高ストレス者の確認と情報提供 実施者は、事前に決めた基準に照らし合わせ、受検者の中に該当者がいるかどうかを確認し、高ストレス者を決定します。この時点では本人の同意が得られていないため、高ストレス該当者を事業者に知らせてはいけません。 -
STEP 2実施者からの面談勧奨 面接対象者に医師による面接指導を受けるよう書面などで勧奨します。また、面接指導を受ける場合は、会社に情報が提供されることになるため、同意書の提出が必要であることを伝えましょう。または、あらかじめ労働者に周知をしておくことで、面接の申出をもって事業者にストレスチェック結果の提供を同意したものとして取り扱うことも可能です。 -
STEP 3医師による面接指導の実施 面接指導の申し出があった場合は、実施日を調整し、勧奨から概ね1ヶ月以内に、医師(産業医など)が面接指導を実施します。対象者の労働時間や労働環境、健康診断などについての情報が面談に必要な場合、事業者から担当の医師へ情報提供します。 -
STEP 4医師の意見聴取 面接指導後、事業者は遅滞なく(概ね1か月以内)医師から「就業上の措置」の必要性に関する意見を聴取することが義務付けられています。 -
STEP 5就業上の措置の決定と実施 事業者は、医師の意見に基づき必要とされる場合には、対象従業員の就業上の措置(配置転換、残業制限など)を行う他、医師の意見を衛生委員会などに報告し、適切な措置を実施することが義務付けられています。
面接指導を案内する際のポイント
高ストレス者への案内は、制度の趣旨と本人の安心感を両立させることが大切です。「会社から呼び出される」といった誤解を避けるため、案内文や説明方法に十分配慮しましょう。
主なポイントは以下の通りです。
1. 案内文は中立的なトーンで作成する
「面接指導は強制ではありません。本人が希望した場合にのみ実施される制度であることを明確にします。また、面接指導を受けるかどうかや、面接指導の内容によって、不利益を被ることは一切ないことを説明します。
2. 守秘義務の説明を明記する
面接指導を申し出ると、面接指導の希望者であることが事業者側に伝えられますが、本人の同意なく面接の内容が事業者へ共有されることがないことを明確に伝えましょう。
3. 案内と回答の記録を残す
案内を行った日付、送付方法、申し出の有無などを記録として残し、制度を適正に運用していることを示せるようにします。また、面接指導を申し出ると、事業者側にその事実が伝えられるため、そのことについての同意を得ましょう。同意の取得は書面又は電磁的記録で行うことが義務付けられています。あとからトラブルにならないよう、記録に残し5年間保存することが望ましいとされています。
ストレスチェック後に面接指導の申し出がなかった場合の対応
面接指導の案内をしても、該当者全員が申し出を行うわけではありません。しかし、制度上、事業者側はそれが誰なのかを特定することはできず、個別にフォローすることはできません。一方で、「企業には全体としての「安全配慮義務」が残ります。個別対応はできなくても、職場全体の状況を把握し、組織単位でのメンタルヘルス対策を進めることが求められます。
たとえば、以下のようなアプローチが有効です。
- ● 実施者から提供される「集団分析結果」を活用し、職場単位でストレス傾向を把握する
- ● 管理者向けに「部下の変化に気づく」「声かけの仕方」などの教育を実施する
- ● 業務負荷や人間関係など、組織的なストレス要因を抽出し、職場環境改善策を検討する
- ● 相談窓口を設けて従業員が相談しやすい環境を整える
個人情報の保護を前提に、「「誰に何をするか」ではなく、「職場をどう良くするか」という視点で取り組むことが重要です。それが結果的に、面接指導を申し出ていない高ストレス者のストレス低減に繋がることになります。
社内で解決が難しいケースは「社外相談窓口」の活用も
ストレスチェック制度を実施しても、面接指導が十分に行われなかった場合、人事・総務担当者には、「制度上のルールは守れたけれど、従業員の悩みを十分に受け止められたわけではないのでは……」という想いが残るかもしれません。
そのような場合は、社内に相談窓口を設け、いつでも相談しやすい環境を作っておくことが望ましいですが、社内に適任者がいないと、実現はなかなか難しいかもしれません。そのような場合は、「社外の相談窓口を併用することが有効です。
特に以下のような問題がある場合は、社外相談窓口がおすすめです。
- ● 産業医の面談を「上司に知られそう」と不安に感じ、申し出をためらっている
- ● 産業医が非常勤で、日程が合わず面談の調整が難しい
- ● 産業医に相談はしたいが、勤務場所が離れているため、距離的に難しい
- ● 医師面談までは踏み切れないが、誰かに話を聞いてほしい従業員がいる
「もこすく相談所でも、ストレスチェックの実施サービスだけでなく、保健師・看護師などの医療職や心理職が、オンラインで従業員様の相談に対応しています。ストレスチェック結果を見て「自分は高ストレス者に該当しているけれど、産業医に話すのは少し抵抗がある」と感じた従業員でも、気軽に相談できる環境です。相談はオンライン形式で行うため、勤務地や勤務形態に関わらず、全国どこからでも利用可能です。 また、企業側にとっても、社外窓口を導入することで、社内担当者の負担軽減や早期対応による休職リスクの低減などの効果が期待できます。もこすく相談所は、従業員のプライバシーを守りつつ、企業のリスク管理にも貢献できる仕組みです。
いますぐプロに相談したい!
もこすく相談所に問い合わせるまとめ
高ストレス者対応は、法令遵守・守秘義務・リスク管理のすべてが求められる業務です。 面接指導の案内方法や申し出後の流れを誤ると、従業員の不信感や法令違反につながるおそれがあります。 特に、「高ストレス者を特定してフォローする」ことは制度上できないため、個人対応ではなく、職場環境全体の改善を軸に対策を行うことが、現場の正しい姿勢です。
もこすく相談所では、産業医・保健師による制度設計の助言、集団分析の結果を活かした職場改善支援、面接指導体制の構築などをトータルでサポートしています。制度の運用や説明方法に不安がある場合は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の要点
- 面接指導は「高ストレス者が希望すれば受けられる制度」であり、義務ではない。
- 事業者は本人の同意がない限り、誰が高ストレス者かを知ることはできない。
- 個人を特定したフォローは不可のため、代わりに「集団分析結果」などを活用し、職場単位で改善を図る。
- 案内文は中立的に作成し、守秘義務を明確に伝える。
- 産業医・保健師との連携により、法令遵守とリスク回避を両立することが重要。
- のべ10万件の相談実績をオンラインで気軽に
- 多角的な視点で幅広いお悩みに対応
- 御社に合ったストレスチェックサービスをご提案
- 包括的なメンタルヘルス対策で離職防止につなげる
ストレスチェックを
有効活用したい企業のご担当者様、
もこすく相談所にぜひお問い合わせください!